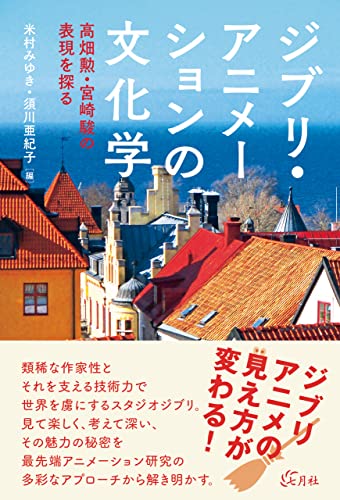ChatGPTの新しいのが公開されて、その画像生成能力がすごいとかで話題になっていた。上手いこと「ジブリ風で」とか指示すると、写真をジブリの絵みたいに加工してくれるらしい。これが物議を醸している。
私はAIを使いこなせていないしまったく進歩についていけていないのだが、これについてはアニメ哲学者*1として物申したいことがある。
まずオタクっぽいことを述べておくと、いわゆる「ジブリ風」の絵というのは、スタジオジブリが設立される前に宮﨑駿・大塚康生・小田部羊一らによって徐々に確立されたものである。↓の本の第1章を読んでほしい。
ジブリを語る際にジブリ以前やジブリ社員じゃない人を無視しないでね、と思っちゃうのがジブリマニアの性。
それはさておき。
つまらない人がつまらないことをやって喜ぶためのツールとしてのAI
ジブリ「風」イラストに嫌悪感を持つ人はけっこう多いようである(楽しんでいる人も多いけど)。私ももちろん好かない。上に挙げた人たちやジブリの人たちが頑張って築いた絵を、お手軽に真似しちゃうのはリスペクトにかける。ただし、ネット上の絵を学習することが法的・倫理的にまずいのかどうかという今ホットな議論に関しては、私にはわからないが。
しかし、しかしである。私がこのジブリ風イラスト騒動で強く思ったのは「あっ、つまんねーな」ということであった。
多くの人がAIを使ってやっていたのは、よくある画像ネタをジブリ風の絵にする、というその程度のことだった。私は「ネットミーム」なるものはつまらないと思っているのだが、ジブリ風イラストもそうしたネットミーム文化の域をまったく出ていない。たんに何かと何かをくっつけているだけである*2特につまらなかったのは、バキバキ童貞のミーム化した画像をジブリ風にしてトゥイッターに挙げていた人である*3。私はあまりのつまらなさに横転。いま顔ない。
AI画像生成って今のところだいたいがこの調子じゃなかろうか。今までもだいたいが二次創作に使われていて、特に斬新なイラストを生成したのを見ない(ちょっとはあったが)。今回もミームとかいうよくわかんないものにばかり使われている。AIってつまらない人が使ってもつまらないものしか生み出せないのだなあ、と思った。
それと自分で撮った何気ない写真をジブリ風にして楽しんでいる人もけっこういた。まあこれは普通な使い方かなと思う。普通の人が普通の使い方をして楽しむのがせいぜいか。
創造性やオリジナリティをいまいちど称賛しよう
そんなわけで、私はまだあまり、AIを使った真におもしろい創作に出会えていない。どれもこれもクリエイティブでない。オリジナルじゃないのである。
創作なんて所詮はコピーだ、みたいな言もあるけれど、私は素朴に、クリエイティブでオリジナルなものこそおもしろいと思っている。創造性とかオリジナリティとか、そういったものをいまいちど衒いなく称賛しましょうや。
ジブリの作品がおもしろいのは、それがジブリ風の絵で描かれているからではなくて、それも含めた全体がクリエイティブでオリジナルだからじゃないのか*4
AIによるアニメ制作とアニメ文化の展望
とはいえ、今後AIを使ったクリエイティブな作品がどんどん生まれるかもしれない。そうなったらどうなるか。特にアニメについて。アニメ哲学者として想像してみる。
まずけっこう恐れているのが、いまアニメーターや美術スタッフがやっている作業をAIで簡単に代替できてしまう場合である。そうなったらアニメーターなどの職業はなくなるかもしれない。これは悲しい。経済学の本でラッダイト運動について読んだのだけれど、それによると、機械化によって職を失った人はかわいそうだが、人類全体にとっては効率化による便益が大きいので、結果的には良かった、という感じらしい。アニメ制作もそうなるかもしれない。
しかしアニメは工業とは違うので、完全にそうなるとも限らない。まったく同じ見た目の絵でも、アーティストが描いたものと非アーティストが描いたものでは違う、というのはアーサー・ダントーの「アートワールド」という有名な論文で論じられていることである。
AIがアニメーターと同じものを描けるとしても、人間が描いたものには異なる価値があるかもしれない。ただしダントーは、画面に一本の線が引かれているだけ、みたいな抽象画をメインの例にしている。アニメはそういうファイン・アートと違うので、何が描かれているかという中身がもっと重要になるだろう。
工業でもアートでもないアニメは、今後を占うのが難しい。むしろ似ているのは、プロの将棋なんじゃないかとも思う。将棋は人間がAIに勝てなくなったが、人間同士の勝負に重きが置かれている。
ところで、AIがアニメーターの仕事を奪うというのも私は変な感じがしている。アニメというのは、アニメーターが手描きすることを前提として発展したジャンルなのだから、手描きしなくてよくなったらAIがアニメーターの様式を真似する必要なんてない。この発想を突き詰めていくと、真にオリジナルなAIアニメが生まれるだろう。私みたいな批評しているだけの愚図にはそれがどんなものか想像もつかないが。
それと、AIでアニメ制作ができるようになったら、アニメを仕事にする人が減り、人類は全体的に絵が下手になるかもしれない。↓の本で読んだが、古代ギリシアで「文字を使うと記憶力が衰えるよ」とか言われていたらしい。
それと似ている。上手い絵を描くことはロストテクノロジーになり、そのため「人間が描いた」ということは大きな価値を持つかもしれない。そう言えば、私はすでにアナログ制作時代のアニメにロストテクノロジーみを感じている。80年代や90年代のアニメは、私には色褪せない魅力を持っているように見える。
総じて、AIがアニメ制作の主流になったら、私は新しいアニメを見なくなると思う。それは私の知っているアニメではなくなるので。まあ今もすでに私は新作アニメをあまり見ないので、それでいいのだが。
*1:私が「アニメ哲学者」を名乗っているのは、アニメについての哲学的な論文を書いたことがあるからね。
cut-elimination.hatenablog.com
*2:ネットミームのこうした性質は↓の『フィルカル』の銭清弘氏の論文で(ネットミームなるものがおもしろいかどうかはともかく)論じられている。
*3:バキバキ童貞に対する私の憎しみは↓を参照。
cut-elimination.hatenablog.com
*4:私は芸術だけでなく学問においてもオリジナリティこそ天才の証だと思っているのよ。